任意後見制度とは
現在は判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が衰えたときに、財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行う人(任意後見受任者)をあらかじめ自分自身で決めておく制度です。
本人の判断能力が十分でなくなったときには、本人や任意後見受任者等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
このときから、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、本人の財産管理や身上監護を行っていきます。
利用の仕方
1.本人と任意後見受任者(任意後見を依頼された人)が任意後見の内容(どのようなサポートをするかなど)を話し合います。
2.本人と任意後見受任者が公証役場で、公正証書を作成し、正式に契約を交わします。
3.本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
4.家庭裁判所で任意後見監督人を選任し、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の下で契約内容に従って本人を保護・支援します。
任意後見監督人選任の申立てのできる人
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
※申立てに必要な書類については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
後見制度利用の費用
≪法定後見制度≫
収入印紙、登記印紙、郵便切手など裁判所に審判を請求する手数料で約1万円が必要となる他、利用者本人の判断能力を確認するための医師の鑑定や診断などで、約5万円~20万円必要となる場合があります。
また、後見等が開始されれば、本人の支払い能力に応じて妥当な報酬を家庭裁判所が審判により決定します。なお、市区町村長が申立人でその利用者が低所得者のとき、自治体によっては、補助を受けられる場合もあります。
≪任意後見制度≫
任意後見受任者は、本人との契約により報酬が決められます。任意後見監督人選任の申立てには、収入印紙、登記印紙、郵便切手などの費用がかかります。任意後見監督人の報酬額は、本人の資力等に応じて家庭裁判所が審判により決定します。
相談できるところ
・お住まいの市区町村の担当課
・地域包括支援センター
・家庭裁判所
・公証役場(任意後見制度)
・弁護士会
・成年後見センター
など

















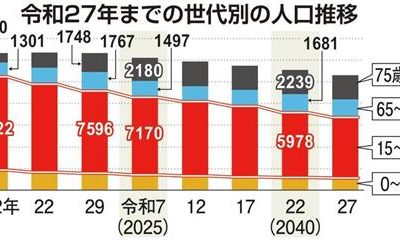




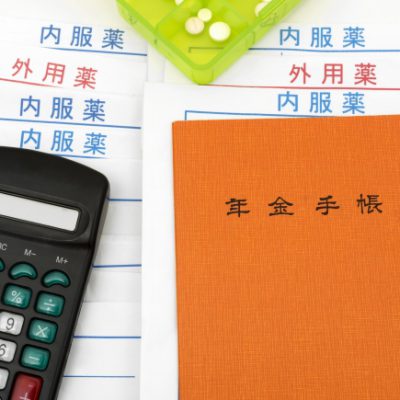




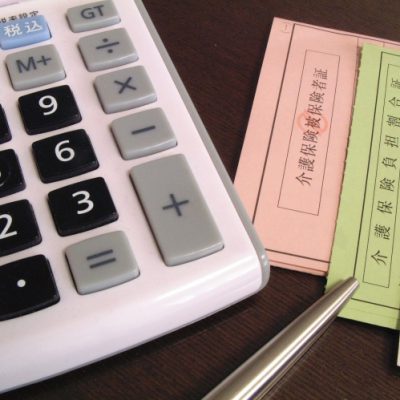

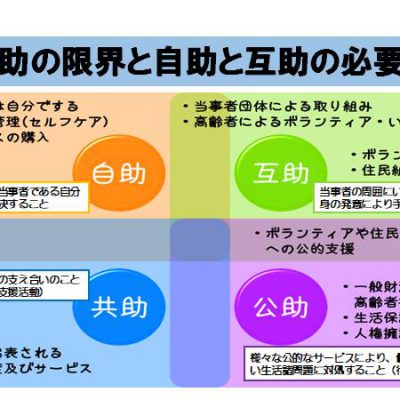





この記事へのコメントはありません。